職場・施設情報
介護施設の種類の覚え方は?施設ごとの特徴と違いを紹介
9 months ago

「介護施設の種類の覚え方がよく分からない」という方もいるでしょう。介護施設の種類は、公的施設か民間施設かの違いや介護保険の適用の有無などによる分類ごとに覚えるのがポイントです。この記事では、介護施設の種類や特徴を紹介します。転職者向けの介護施設の選び方も働き方別に紹介するので、ぜひ参考にしてください。
介護施設の種類の覚え方は?
介護施設には多くの種類があり、特徴ごとに分類すると覚えやすくなります。ここでは、介護施設の種類の覚え方を3つ紹介します。
運営元の違いで覚える
介護施設の種類の覚え方として、運営元の違いに着目する方法があります。介護施設の運営元は、公的施設と民間施設に分類できるのが特徴です。
公的施設の場合、地方公共団体や社会福祉法人、医療法人などが主な運営主体となります。一方、民間施設の場合、株式会社や合同会社といった営利法人による運営が一般的です。
介護保険の適用の有無で覚える
介護施設の種類は、介護保険の適用の有無による覚え方もあります。
介護保険が適用される介護施設の場合、適用外の施設に比べると、利用条件が厳しい施設が多いのが特徴です。
その一方で、介護保険適用の施設の場合、所得が低い方なども利用できるよう、費用が比較的安く設定されている施設が多い傾向にあります。
入居型・通所型の違いで覚える
介護施設の種類は、入居型・通所型の違いで覚える方法もあります。
入居型の場合、介護サービスが付いている施設と、必要に応じて外部の介護サービスを利用する必要がある施設に分けられます。また、一般的な「介護施設」ではなく、「高齢者向けの住まい」と捉えられる施設もあるのが特徴です。
通所型介護施設には原則、寝泊まりできる設備はなく、日帰り利用となるため、利用者宅への送迎サービスがある施設が多くみられます。
主な介護施設の種類一覧
主な介護施設の種類一覧は次のとおりです。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 介護付有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- 健康型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 通所介護(デイサービス)
- 小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
以下で、それぞれの介護施設の詳細を紹介します。
介護施設の種類の覚え方:公的施設
ここでは、公的施設にあたる5種類の介護施設を紹介します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
厚生労働省「介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」によると、介護老人保健施設(特別養護老人ホーム)とは、要介護者のための生活施設です。介護老人保健施設は、入居者に対して、食事・排泄などの介護や機能訓練、療養上の世話などの介護サービスを提供する介護保険施設となっています。
介護老人保健施設の入居者は要介護認定を受けた方が対象で、要支援1・2の方は利用できないのが特徴です。また、やむを得ない理由がある場合を除き、要介護1・2の方の入居も原則認められていません。そのため、介護老人福祉施設の入居者は、要介護3~5の方が大半を占めています。
介護老人保健施設
厚生労働省「介護老人保健施設」によると、介護老人保健施設とは、要介護者に対して、在宅復帰や在宅療養支援を行う介護保険施設です。「老健」と呼ばれることもあります。
前述の介護老人福祉施設が生活施設である一方で、介護老人保健施設は、在宅復帰を目的としているのが特徴です。そのため、介護老人保健施設では、入居者が自宅に帰るためのリハビリや生活訓練、医学的な管理・看護などが行われます。
また、介護老人保健施設の場合、要介護1~5の方も利用できるのも特徴です。
介護医療院
厚生労働省「介護医療院公式サイト」によると、介護医療院とは、要介護者へ長期療養のための医療と、日常生活上の世話を一体的に提供する介護施設です。
介護医療院は、2018年度に創設された介護保険施設で、2024年3月に廃止された「介護療養型医療施設(介護療養病床)」からの移行先として位置づけられています。生活施設としての機能に加えて、日常的な医学管理や看取り・ターミナルケアなどにも対応しているのが特徴です。
軽費老人ホーム(ケアハウス)
厚生労働省「IV.その他のサービス 養護老人ホーム、軽費老人ホーム」によると、軽費老人ホームとは、無料または低額な料金で入居できる高齢者向けの施設のことです。
なお、軽費老人ホームのうち、自炊ができない程度の身体機能の低下が認められたり、一人暮らしや家族による援助が困難であったりする高齢者を対象とした施設は「ケアハウス」と呼ばれます。軽費老人ホームには、ケアハウス以外にもA型やB型などがありますが、大半がケアハウスであるのが特徴です。
また、軽費老人ホームでは、外部の介護サービスを利用するのが一般的ですが、「特定施設入所者生活介護」の指定を受けたケアハウスの場合、介護保険の対象として、施設内で介護サービスを提供できます。
通所リハビリテーション(デイケア)
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの?-通所リハビリテーション(デイケア)」によると、通所リハビリテーションとは、利用者が自宅で自立した日常生活が送れるよう、食事や入浴など日常生活上の支援や生活機能向上のための機能訓練などを提供する介護サービスのことです。
通所リハビリテーションは、日帰りで提供されるサービスであることから、「デイケア」と呼ばれることもあります。通所リハビリテーションの施設は、老人保健施設や病院、診療所などに併設されているのが一般的です。
参考:厚生労働省「第221回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」
厚生労働省「介護医療院公式サイト」
厚生労働省「第8回社会保障審議会介護保険部会」
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの?-通所リハビリテーション(デイケア)」
介護施設の種類の覚え方:民間施設
ここからは、民間施設にあたる介護施設の種類を8つ紹介します。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
厚生労働省「認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)」によると、認知症対応型共同生活介護とは、認知症の高齢者に対して、日常生活上の世話や機能訓練などを行う施設のことです。
認知症対応型共同生活介護は、5~9人の利用者が一つの共同生活住居(ユニット)で、共同生活を送ることから、「グループホーム」と呼ばれることもあります。認知症対応型共同生活介護では、1事業所あたり1~3つのユニットが運営されているのが一般的です。
認知症対応型共同生活介護の利用対象は、要支援2または要介護認定を受けた方と定められています。2019年4月の調査によると、認知症対応型共同生活介護の入居者の平均要介護度は2.74となっており、入居者の要介護認定度が比較的低いのが特徴です。
介護付有料老人ホーム
厚生労働省「別表 有料老人ホームの類型」によると、介護付有料老人ホームとは、介護サービスが付いた高齢者向けの居住施設のことです。
介護付有料老人ホームには「一般型特定施設入居者生活介護」と「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」の2種類があります。一般型の場合、介護サービスは有料老人ホームの職員が行いますが、外部サービス利用型の場合、委託先の介護サービス事業所によって介護サービスが提供されるのが特徴です。
いずれの場合でも、介護付有料老人ホームでは、介護が必要な状態になっても、入居者は引き続き有料老人ホームで生活を続けられるのも特徴の一つといえます。
住宅型有料老人ホーム
厚生労働省「別表 有料老人ホームの類型」によると、住宅型有料老人ホームとは、生活支援などのサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
住宅型有料老人ホームでは、施設からの介護サービスの提供がありません。そのため、介護が必要となった場合、入居者自身で地域の訪問介護などの介護サービスを選択・利用しなければならないのが特徴です。
健康型有料老人ホーム
厚生労働省「別表 有料老人ホームの類型」によると、健康型有料老人ホームとは、食事などのサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
健康型有料老人ホームでは、介護サービスを受けながら居住することは認められていません。そのため、介護が必要となった場合、契約を解除し、退去しなければならないのが特徴です。
なお、国土交通省「データから見た高齢者住宅・施設の需給バランス」によると、2020年10月現在、類型ごとの有料老人ホームの施設数は、介護付有料老人ホームが4192件、住宅型有料老人ホームが1万508件なのに対し、健康型有料老人ホームは全国で20件となっています。
健康型有料老人ホームの件数は、ほかの類型に比べると、施設数が非常に少ないのも大きな特徴の一つです。
サービス付き高齢者向け住宅
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス付き高齢者向け住宅について」によると、サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者単身や夫婦世帯が居住できる賃貸の住まいのことです。「サ高住」と略されることもあります。
サービス付き高齢者向け住宅では、安否確認サービスと生活相談サービスが提供されるのが特徴です。なお、サービス付き高齢者向け住宅は正式には介護施設ではなく「住まい」という位置付けであるため、入居者が介護サービスを利用する場合は、入居者自身が必要に応じて、介護サービス事業者を選択・利用します。
また、厚生労働省「高齢者向け住まいについて」によると、サービス付き高齢者向け住宅の入居対象者は、60歳以上の方もしくは要介護認定を受けている60歳未満の方です。なお、賃借人の配偶者や60歳以上の親族、要介護認定を受けている親族なども同居できる特徴があります。
通所介護(デイサービス)
厚生労働省「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護」によると、通所介護(デイサービス)とは、要介護者に対して、入浴・排泄・食事の介護や生活に関する相談・助言、健康状態の確認、機能訓練などを行う通所型の介護施設のことです。
同資料によると、2021年現在、通所介護の利用者の平均要介護度は2.2となっており、要介護度1・2の方が全体の6割以上を占めています。通所介護では、サービスの提供が通所介護施設の利用時間内に限定されていることもあり、要介護度が比較的低い利用者が多いようです。
小規模多機能型居宅介護
厚生労働省「小規模多機能型居宅介護」によると、小規模多機能型居宅介護とは、利用者の要望に合わせて、通所利用や居宅への訪問、施設での宿泊などを組み合わせたサービスを提供する介護施設です。「小多機」と呼ばれることもあります。
小規模多機能型居宅介護では、食事・入浴・排泄の介護や調理・洗濯・掃除などの生活支援、機能訓練などが行われます。
同資料によると、2018年度の調査における小規模多機能型居宅介護の利用者の平均要介護度は2.2です。小規模多機能型居宅介護は、施設に通い、サービスを受ける形が基本となっていることから、要介護度の平均は比較的低い傾向にあります。
一方で、要介護度が高くなるにつれ、「通い」「訪問」「泊まり」のサービスを組み合わせたサービスの利用が増える傾向にあり、要介護度が高い利用者のニーズも一定以上あるといえるでしょう。
短期入所生活介護(ショートステイ)
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの?-短期入所生活介護(ショートステイ)」によると、短期入所生活介護とは、介護が必要な利用者が短期間だけ入所し、日常生活上の支援や機能訓練などを受けられる介護サービスです。短期入所生活介護は、原則30日まで連続して利用できます。
短期入所生活介護は、要介護認定を受けた方を対象としており、普段介護を行っている家族の身体的・精神的負担の軽減の役割も担っているのが特徴です。そのため、利用者自身の心身の状態や病状が悪い場合だけでなく、家族が一時的に介護から離れて休息をとるために、短期入所生活介護を利用するケースもあります。
参考:厚生労働省「第179回社会保障審議会介護給付費分科会(オンライン会議)資料」
厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」
国土交通省「サービス付き高齢者向け住宅に関する懇談会 第5回配布資料」
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス付き高齢者向け住宅について」
厚生労働省「第102回社会保障審議会介護給付費分科会資料」
厚生労働省「第219回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの?-短期入所生活介護(ショートステイ)」
向いている人別にみる介護施設の種類の選び方
ここまで、介護施設の種類や特徴をみてきました。では、介護施設で働く際、どのように介護施設を選ぶと良いのでしょうか。ここでは、向いている人別に、介護施設の種類の選び方を紹介します。
介護スキルを磨きたい人
介護スキルを磨きたい人は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設など、要介護度が高い利用者の受け入れを行っている介護施設がおすすめです。介護老人福祉施設や介護老人保健施設では要介護度が高い利用者が多いため、入浴介助や車いす移乗、排泄介助など、身体介護に携わる機会が多くなります。日々の業務を通して、自身の介護スキルを磨けるでしょう。
体力に自信がない人
体力に自信がない人は、身体介護が比較的少ない健康型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅での勤務がおすすめです。サービス付き高齢者向け住宅の場合、基本的に介護サービスは外部の事業者によって提供されます。よって、サービス付き高齢者向け住宅での職員の主な業務は生活援助となるため、体力に自信がない方も比較的働きやすいでしょう。
また、健康型有料老人ホームの利用は、介護を必要としない方が原則となるため、身体介護を行う機会は極めて低いといえます。ただし、健康型有料老人ホームは施設数が少ないため、職場探しが難しい場合もあるでしょう。
仕事とプライベートを両立したい人
仕事とプライベートを両立したい人は、夜勤のない通所リハビリテーションや通所介護などがおすすめです。これらの施設では、施設の利用時間も決まっていることから、大幅な残業が発生する可能性は低いと考えられます。そのため、子育て中や介護中の方も比較的働きやすい職場が多いでしょう。
給与の高さを重視したい人
給与の高さを重視したい人は、入居型の介護施設を選ぶと良いでしょう。
厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、2022年9月時点の介護職員の施設別平均給与額(月給制・常勤)は以下のとおりです。
| 介護施設の種類 | 平均給与額 | |
|---|---|---|
| 入居型 | 介護老人福祉施設 | 34万8040円 |
| 介護老人保健施設 | 33万9040円 | |
| 介護医療院 | 32万700円 | |
| 認知症対応型共同生活介護事業所 | 29万1080円 | |
| 入居・通所型 | 小規模多機能型居宅介護事業所 | 28万7970円 |
| 通所型 | 通所リハビリテーション事業所 | 30万4790円 |
| 通所介護事業所 | 27万5620円 | |
| 31万7540円 | ||
参考:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」
入居型介護施設の場合、夜勤があることから、通所型に比べると平均給与額が高い施設が多い傾向にあります。また、要介護度の高い利用者が多いことから、賃金の設定が高めなケースも多くみられるでしょう。
参考:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」
介護施設の種類の覚え方は運営元で分ける方法がある
- 介護施設の種類の覚え方の分類は、介護保険の適用の有無や運営元の違いなどがある
- 公的施設である介護施設の種類には、特養や介護老人保健施設、介護医療院などがある
- 民間施設である介護施設の種類には、有料老人ホームや小多機、サ高住などがある
- 介護スキルを磨きたい人が転職する際は、特養や介護老人保健施設などがおすすめ
関連記事
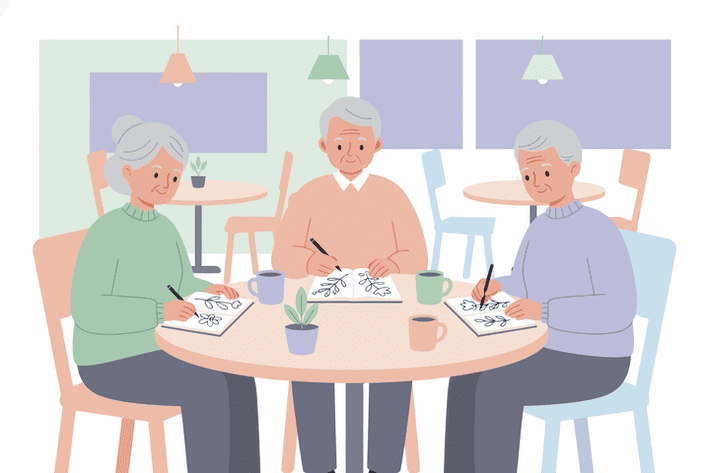
NEW
介護レクのマンネリ打破!利用者が五感で楽しめるサービスを紹介

NEW
介護・医療現場に「温かいケア」を届ける、注目の団体を紹介

NEW
笑顔あふれる介護のために!自立とゆとりを支える注目の取り組み
おすすめ記事
人気のエリアから求人を探す
介護士・ヘルパーの求人を都道府県・主要都市から探す




